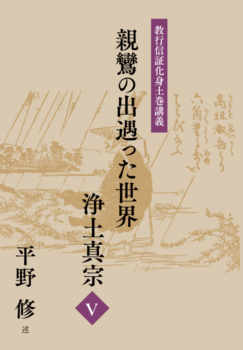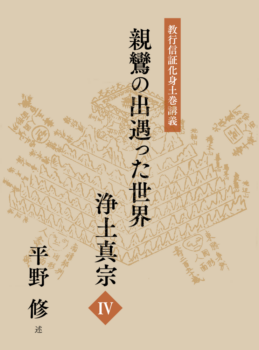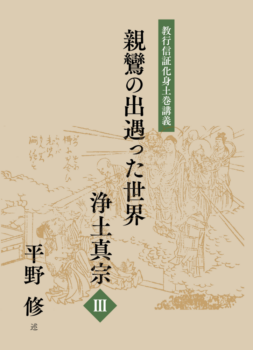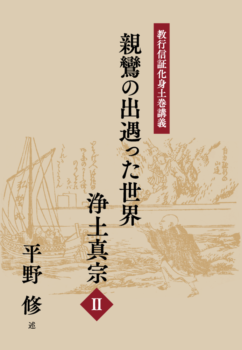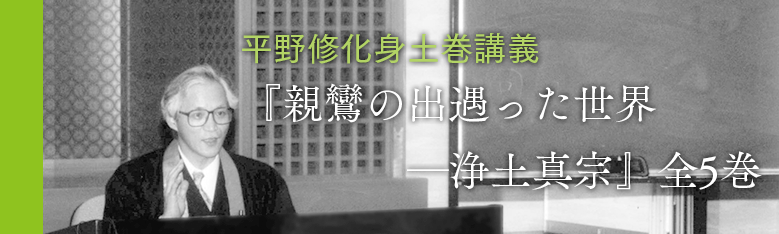
平野修師が病床に伏される直前まで続けられた未完にして最後の大講義、ついに完結!
大阪教区教学研修院の基調講義として8年間、全46回にわたり行われた「化身土巻講義」を全5巻にわけて収録。「化身土巻」の内容から、仏教の歴史、そして親鸞聖人のみ教えを徹底的に俯瞰し、私たち自身に問いを投げかける平野修師の思想の集大成ともいえる書です。
どの回の講義においても平野先生の念頭には常に、親鸞聖人が出遇い、誕生し、そしてその生涯をかけて顕かにしようとされた本願念仏の仏教があったのではないでしょうか。平野先生がお亡くなりになって二十五年が経とうとする今日、この講義にひとりでも多くの方が触れてくださることを切に念願するものです。
(第1巻編集後記・高間重光)
ご注文は大阪教務所(TEL06-6251-4720/FAX 06-6251-4796)または、osaka-shuppan@higashihonganji.or.jpまで。
→内容見本(PDF) 第Ⅰ巻第一講をお読みいただけます
第5巻(2025年6月30日発刊)
目次
第三八講 善知識論
第三九講 信不具足
第四○講 真実第一の善知識としての仏
第四一講 仏言としての南無阿弥陀仏
第四二講 如来より証明された自分自身
第四三講 願意へのうなずきと親鸞の名告り
第四四講 流転の根源への覚知
第四五講 僧伽の成立と浄土真宗の名告り
第四六講 釈尊中心主義から二尊教へ
編集後記全文
一九九五年三月二七日に行われた第四六講「釈尊中心主義から二尊教へ」のあとしばらくして、平野先生は体調を崩し入院されました。そして一九九五年の九月二七日、満五十二歳でご逝去されました。それからちょうど三十年になろうとしています。
本講義は当時、大阪教区教学研修院の基調講義として、一九八七年九月より一九九五年三月まで全四十六回にわたって行われ、その講録を『生命の足音―教化センター紀要』(大阪教区教化センター発行)に掲載していたものです。
選集にも収められていないこの講義録を、ぜひまとめて読めるよう単行本にしてほしいとの強い要望があり、大阪教区教化委員会「広報・出版部」で出版する運びとなりました。当時、教化センターに在籍して、直接平野先生のお話を聴講していた人たちを中心に「平野修師講義集」編集実行委員会を立ち上げ、およそ五年の月日をかけて全面的に再校正を施し、全五巻を上梓するに至りました。
本書は「化身土巻」を通して、先生の仏教観、親鸞観が如実にあらわれた講義であり、未完とはいえ宗門にとっても非常に大切な内容ではないかと思っています。そんな書籍を大阪教区として出版することができましたことは、光栄の至りであります。三十年を経てなお輝きを失わないこの講義が、教区や宗派を越えて、さらに広く読まれることを念願しております。
最後になりましたが、出版をご快諾いただいた明證寺様、また編集実行委員会で校正にご尽力いただいた浅野景司氏、池田剛氏、鹿崎正明氏、髙間重光氏に、改めて感謝の意を表します。ありがとうございました。
二〇二五年六月
大阪教区教化委員会「広報・出版部」前幹事 澤田 見
幹事 大戸俊彦
第4巻(2024年3月10日発刊)
目次
第二九講 真門の方便
第三○講 果遂の誓い
第三一講 仏が選択し勧められる念仏
第三二講 疑心を転ずる仏言
第三三講 就人立信
第三四講 苦悩の因を自身にたてる真宗
第三五講 信仏による仏の証明
第三六講 仏来迎の意義
第三七講 信心を表す執持名号
編集後記全文(池田 剛)
一九八七(昭和六二)年八月大阪教区教学研修院が開設されます。その基調講義を担っていただくお一人が、平野修師でありました。ただそれまでに、センター主催の『化身
土・末巻』の講義に出講されていましたので、引き続き我々に視座をいただくことになりました。
平野師と最初に出会ったのは、大阪教区教学研修院が始まる一年半程前のことで、センター主幹であった本多恵師が、まだ静岡別院の輪番をされていた頃です。その頃平野
師は、九州大谷短期大学で教えておられましたが、全国の青年達が出会っていく場を創造し、地域の問題・課題を一人ひとりの問題・課題として見つめていく歩みを、当時東
本願寺宗務所に設置されていた青少年部の依頼で、青少年部のスタッフと共に「青年研修会」を進めておられました。本山に集まって開催されていた研修会を、各地域で活動
している青年を結んでいく願いもあり、各地域での研修会開催となっていきました。平野師は、第七回から第十二回までの講師として、そしてスタッフと共に企画する一人と
して、参画しておられました。
一九八六(昭和六一)年二月に、静岡別院を会場に開催されたときの参加者の一人でありました小生ですが、それ以来、師が亡くなる日までお世話になり通しでありました。
思い出されるのは、師に迷惑をかけたことばかりです。ある研修会の講師をお願いするため日程を相談したとき、手帳には半年先まで全国へ行く予定で埋め尽くされていまし
た。そんな中、無理を承知でお願いをしましたところ、時間をつくって来てくださいました。
一九九五(平成七)年七月に松任市で開催された「青年研修研究集会」での講義が、聴かせていただいた最後の言葉になりました。いつも我われに、激しくはなく淡々とし
た口調ではありましたが、本当に教えの言葉を紡いでいただきました。小生も歳を重ねる中で、平野師の恩を少しでもおかえしすることができればと、この講義録の編集に参
加させていただいたことです。
平野師との出会いが無かった方たちにも、読んでいただければと憶うばかりです。
二〇二四年三月
「平野修師講義集」編集実行委員会 池田 剛
第3巻(2023年4月1日発刊)
目次
第二○講 浄土の真宗
第二一講 正行・雑行と雑修
第二二講 不回向の行
第二三講 行の選択
第二四講 方便の真門
第二五講 本願の仏教
第二六講 『小本』の顕彰隠密の
第二七講 大乗無問自説経
第二八講 信心為要
編集後記全文(鹿崎正明)
この巻の最初のところに、このような文章があります。
もし「真宗ってどのような教えですか」と言われて答えられないということになりますと、真宗の教相が理解できていないということになります。
その点では、真宗の教相は、真宗の門徒であるとみずからいっている人たちの中においても、実にあいまいなものになってしまっています。(本書一六頁)
真宗門徒といっている私たちのありさまを、実にうまく、いいあてられています。
平野先生の 「化身土巻」 の講義を改めて読み直してみて、こんなに丁寧な教相の話を聞いていたのだと改めて認識しました。
当時、 大阪教区教化センターに勤めていた私は、毎回先生の話を聞かせていただき、それを『南御堂』紙のセンター面に掲載するため、またセンターの紀要『生命の足音』に掲載する原稿とするため、テープ起こしをしたり、また人に頼んだテープ起こしの原稿を聞きなおしたりと、何度も何度も先生の講義を聞きました。また、文章の整理や校正で何度も何度も読み返しもしました。しかし今、改めて読み返してみると、こんな話をしておられたのかと、この講義の内容に驚いています。
その時々の自分の関心で読んでしまいますから、三十年近く時がたつと、 大事なところはほとんど記憶になく、こんなに深く丁寧な講義だったのだと、その時に気づけなかった自身の浅さをつくづく思い知らされます。 『教行信証』 特に「化身土巻」 は、 人間の心の闇の深さを深く見つめておられた親鸞聖人の眼によって見出された世界です。それを先生は、丁寧に一文ずつ考察し、話してくださいました。
当時先生はお忙しかったので、各地への移動の列車の中などで、原稿に手を入れたり、校正を見ているとお聞きしていましたが、先生がおられるときには、文章を整理し、校正をしていても先生が目を通されているのだからという甘えがあるものですから、あまり深く読むことなく、そのまま活字化したこともありました。
今また先生の講義を新たに出版するにあたり、先生がおられない以上、できる限り雰囲気を残しながら先生の真意を伝わりやすくするために、表現を変えたところもあります。今、文章を読んでいると、先生が目の前で少し伏し目がちに話されているお声が聞こえてくるような気がします。
二〇二三年三月
「平野修師講義集」編集実行委員会 鹿崎正明
第2巻(2022年2月1日発刊)
A5上製本/388ページ
頒価2,300 円(送料別途)
目次
第一一講 曇鸞から善導における信の展開
第一二講 衆生の発起する願生心
第一三講 理想と現実との認識から出発
第一四講 善導独明の仏教史観
第一五講 観経の二義
第一六講 選択本願を宗とする三経
第一七講 浄土の要門
第一八講 真実報土の真因
第一九講 真宗の教相と仏教の歴史
編集後記全文(浅野 景司)
一九八〇年以来、大阪教区教化センターでは、時代社会から教団に問われている大きな課題としてあった、同和・靖国問題に学ぶスタッフ学習部門を設けて活動してまいりました。
その活動の中から見えてきた「浄土と国家」をテーマとして、一九八五年二月十六日に平野修師を招き、「浄土の思想から見えてくるもの 真宗と靖国」を講題に公開講座を開催しました。そして一九八五年九月から一九八七年七月まで『化身土・末巻』の講義をしていただき、難波別院から『鬼神からの解放』として出版していただきました。
教化センターは、本夛惠氏を主幹に迎え、一九八七年一月一日に新発足し、同年七月から、廣瀬杲師の「教行信証総説」、平野修師の「教行信証化身土巻」を基調講義とした大阪教区教学研修院が始まりました。これにより、一九九五年三月まで四十六回の平野修師の講義を受けることができました。
そして、講義のテープ起こしをして、『南御堂新聞』の教化センター面へ抄録を載せたり、教化センター紀要『生命の足音』に講義録を載せるため、何度もテープを聞き 直したり、平野先生からの朱の入った原稿や、出稿したゲラ刷りを読み直し、何度も何度も目にしていたにもかかわらず、今回読み直していると、こんなことをおっしゃっておられたのかと、まるで初めて読むかのような感覚でした。いかに自分の中に入っていなかったのか。聞いたつもりに 、読んだつもりになっていたことを思い知らされる羽目になりました。
研修院の講義の後、平野先生はほぼ毎回研修院生等と共に食事に行き、そこで様々なことを語り合われました。講義の時とは違い、にこやかに時には厳しく語られていました。ある時誰かが、「真宗聖典がなかなか読めません」と言うと、先生は、「真宗聖典を読む時は自分なりの結論をだしながら読んでいき、分からなくなったらまた最初から読み直します」とおっしゃいました。それは誰もがしている、あたりまえのことだといわれているような気がしました。
帰り際には、 いつも参加者からの贈り物である山葵を一本持ってホテルへ向かわれ た姿を思い出します。
二〇二二年一月
「平野修師講義集」編集実行委員会 浅野 景司
第1巻(2021年2月1日発刊)
A5上製本/376ページ
頒価2,300 円(送料別途)
目次
第一講 化身土巻を読む視点
第二講 題号と標挙
第三講 権実・真仮の分判
第四講 方便化身の浄土
第五講 願往生心の内省
第六講 経典のもつ二重性
第七講 逆縁興法
第八講 顕彰隠密の義
第九講 別意の弘願
第一○講 定散の心と念仏の信
編集後記全文(高間 重光)
本書における平野修先生の『教行信証』化身土巻講義は、大阪教区教学研修院の基調講義として一九八七年九月から一九九五年三月まで隔月ごとに四十六回にわたり講義されたものです。思いがけずも最終講義となってしまった第四十六講は、三願転入の文に続く自釈のところで終わっています。
毎回の講義は、まずその回に読もうとする箇所がどのようなテーマを持っているのか、また先回の内容とどうつながっているのか、さらにはその内容が『教行信証』各巻とどのように関連しているのかに触れた上で、その回に読もうとしている自釈・引文の言葉に丁寧にあたっていかれました。したがってその講義内容は、単に化身土巻だけにとどまるものではなく、『教行信証』全体を視野に入れたものでもありました。そのような平野先生の講義スタイルは、全体を学べば文言が読めず、文言を学べば全体が見えてこないという私たちへの配慮であったのかもしれません。
そして、聖典を学べば、その言葉の対象的な学びにとどまり、自分自身を欠落させてしまう私たちに対して、第六講では、
事細かに『教行信証』の言葉を詮索することでその意味を明らかにしようとしますと、非常に教理的になってきます。それは『教行信証』の中に真宗があると考えるからです。『教行信証』は、真宗・仏教とは自身が成就するという在り方である、と教えています。『教行信証』を文字の上で理解したからといって真宗が分かるということではないでしょう。
と話してくださっています。
また、浄土真宗においては要となる事柄でありながら、私たちに容易に明確になりえない「信心」について第四十一講では、
「専修にして雑心なるものは大慶喜心を獲ず」。この大慶喜心というのは『教行信証』の中での使い方からすれば、信心を現す言葉です。信心ということで親鸞が表そうとする問題は、自己自身ということです。仏・如来より証明された自分自身が信心です。
と具体的に表現してくださっています。
また蓮如上人五百回御遠忌を控えての時期でもあった当時、その教えについてもしばしば触れられておられます。第三十六講では、
蓮如は『教行信証』をよくよくお尋ねになられた。そしてそこに行と信の事柄をはっきり了解なさった。その表現が「仏たすけたまえ」という言葉です。我われの方が「たすけたまえ」を、あてもないことを頼む行だと考えてしまうのです。しかしそれは、行ではなく信を表す言葉です。このように、実に深い『教行信証』の了解があって『御文』ができていると理解されるところが随所に見受けられます。
と講義されています。また当時の様々な社会事象にも触れられて、第四十五講では、渦中になったオウム真理教の問題についても話されています。
そして、結果的には最終講となった第四十六講を目前にして、三願転入の文を内容とした第四十三講では、
「ここをもって、愚禿釈の鸞」という言葉ですが、「ここをもって」というのは、十九願・二十願が意味するところの「わが力でわが身をたすけることはできない」というこころが了解できたと。その了解できたことによって生まれ出るものが「親鸞」という名です。もっと言えば、仏の願に触れて生まれ出るものは、自分自身である。
と講義されています。
このように、この第四十三講に限らず、どの回の講義においても平野先生の念頭には常に、親鸞聖人が出遇い、誕生し、そしてその生涯をかけて顕かにしようとされた本願念仏の仏教があったのではないでしょうか。平野先生がお亡くなりになって二十五年が経とうとする今日、この講義にひとりでも多くの方が触れてくださることを切に念願するものです。
二〇二一年二月
「平野修師講義集」編集実行委員会 高間 重光
Last modified : 2025/07/19 13:08 by 第12組・澤田見(組通信員)