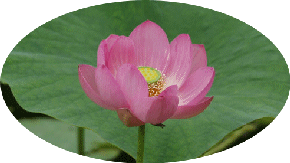
「に」ではなく「を」憑(たの)む
以前、国語科の教員をしていた時のことを思い出しています。たしか、「に」「を」「へ」など、いわゆる助詞の微妙な働きと違いについて学習する場面でした。
昔のこと、とある田舎の夕方の光景です。庭先に古びた井戸があり、擬ね釣瓶(はねつるべ)で水を汲んで、主婦がお米を洗っています。用水路も流れ、夕暮れの中で、てきぱきとお米を洗うしぐさや、お米の白さまでが眼に浮かんで来るようです。
折りから、そこへ蛍が2、3匹、水を求めて飛んで来ました。その時の趣きを詠んだ俳句ですが、
①米洗う前へ蛍が二つ三つ
②米洗う前に蛍が二つ三つ
③米洗う前を蛍が二つ三つ
問題は、①、②、③それぞれの俳句の「へ」「に」「を」のもっている微妙な味わいの違いです。
①は、どこからともなく蛍が2、3匹、米を洗っている前へ飛んで来たという感じですね。②は、米を洗っている前にということで、ピタッと蛍がはりついている味わいになります。③になるとどうでしょうか。米を洗っている前を、あっちへ行き、こっちへ行きと、自由自在に飛び回っている動きを感じ取ることができるようですね。ざっとこのような内容だったと思います。
さて、私たちは日頃、信心をいただき、また往生極楽のみちを問い聞かせていただこうとお寺にお参りし、その都度、法話を聴聞させていただいています。
ところで、日常生活の中で、お念仏とは、私の願いがかなえられることではありません。お念仏とは、阿弥陀さまにたのむのではなく、阿弥陀さまをたのむことなのです。「阿弥陀さまをたのむ」と、「阿弥陀さまにたのむ」とは全く意味が違います。「阿弥陀さまにたむ」は、自分の力ではかなわないからと自分の思いをかなえてもらおうと頼むことです。
私たちは、自分の力で何とかすれば何とかできると自分のを頼んで力(りき)んで生きていますが、このような人を親鸞聖人は「自力」と批判され、「わが身をたのみ、わが心をたのむ、わが力をはげみ、わがさまざまな善根をたのむ人」と言っておられますが、このこと自体が「自力」(じりき)であり、迷いなのです。「阿弥陀さまをたのむ」とは、自力の無効なこと、迷いであることに目覚めて、自力をひるがえして阿弥陀さまを憑(たの)むことです。
この「憑む」は、「ああしてください、こうしてください」という注文の心を捨てて、幸も不幸も、善も悪も、生も死もすべてを阿弥陀さまにおまかせし切って安心して日々を重ねることのできる確かな足場に立って、本当の意味での生きる勇気を賜わることなのです。
思い通りになってもならなくても、私は、この人生をありのままに受け取って歩ませていただくということです。私たちの人生には、よいことばかりではありません。悪いこともあります。受けなければならないものは、受け取っていかなければなりません。「よきことも、あしきことも、業報にさしまかせて、ひとえに本願をたのみまいらすればこそ、他力にてはそうらえ。」(『歎異抄』)とお示しになっています。
よきことも、あしきことも業報におまかせする。これが本願をたのむ、如来をたのむ、他力をたのむということなのです。
わが身を深く頼み、力んでいることこそが迷いの根本であったと知らしめ、阿弥陀さまにおいてすでにおさめとられてあった私自身であったと目覚めしめられるお呼びかけが「弥陀をたのめ」のみ教えなのであります。
このように大事なのは「を」です。「に」とは違います。
親鸞聖人の教えの中には「に」は出て来ません。
阿弥陀さまに、一つたのみますというのでなく、阿弥陀さまをたのむのです。おまかせをするのです。ここに真宗のすばらしい教えがあります。
(平成4・7・11)
Last modified : 2014/12/10 3:20 by 第12組・澤田見(ホームページ部)







