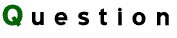
香典の表書きは「御霊前」と書くのが普通ですが、真宗だけはなぜ「御香資」「御香儀」と書くのですか。
(38歳・男性)
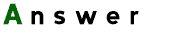
社会生活をしている私たちにとっては、冠婚葬祭は避けて通れない世のならわしです。その時どきの作法は、これまた私たちの気になることです。その一つとして葬式があるわけです。葬式に参列するとき問題になるのが香典です。
香典については、死者の霊前にそなえる香に代わる金銭のことだというのが一般的解釈であるようです。そこで、あなたがおっしゃるように、実際に一般には「御霊前」と書かれ、真宗だけが「御香資」「御香儀」と書いているのでしょうか。他の仏教の宗派はいかがなものでしょうか。
と申しますのは、こと仏教におきましては、葬式は仏事を行う儀式です。真宗に限ったことではないはずです。葬式はこの世を去って行かれた方を縁として、別れを悲しみ、僧侶を中心として一般参列者ともどもに、仏法の事業(じごう)を行うということでなくてはなりません。
仏事を行うには、まず身心を清浄に保つことから始まります。そこで具体的には「香華をそなえる」ということが教えられています。華花は身を清浄に、香は心を清浄に、ということを象徴しているかと思われます。
真宗の源流を開示されたとも言われる中国の善導大師が『法事讃』という書物を残されて、浄土教の儀式について述べられております。それを受けて真宗では、葬式の主旨を「香華をそなえ、仏徳を讃嘆し、生前の遺徳をしのぶ」としています。
「御香資」の資とは「たすく」という意味です。仏事である葬式をたすける、援助する、さらには、参加させていただくという意味で、この表書きは適切であろうかと思います。
「御霊前」という場合、霊ということについては一考を要しますが、私たちの気持の中では亡くなられた方にそなえるという思いがあろうかと思われます。しかし、仏教徒としては不適切な表現です。
(本多惠/教化センター通信 No195)
Last modified : 2014/12/09 6:17 by 第12組・澤田見(ホームページ部)







