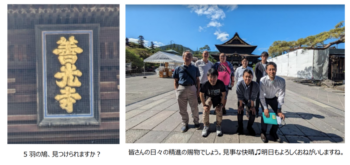13組 坊守会 日帰り研修旅行
- 2024年07月09日(火)11:12
- コメント: 0
先日、13組坊守会で奈良・吉野下市にある『歎異抄』の著者(とされる)唯円坊終焉の地と伝えられる「立興寺」さんに研修旅行に行ってきました!
前日から大雨の予報が出ていたので心配しながらのスタート☔☔☔(・・;)
ご住職がお話くださった「身代わりの名号」という伝説では、平次郎(後の唯円)は仏法に興味がなく、妻の方が親鸞聖人の熱心な信者でした。
妻は親鸞聖人から「南無阿弥陀仏」のお名号をいただき、夫に隠れて毎晩お名号に向かって手を合わせていました。平次郎は妻の行動に不信感を抱き(浮気しているのでは!?)帰りを待ち伏せて斬りつけましたが、妻は無事でした。ふとお名号を見ると刀傷が入っており、平次郎は妻の信心によって命が守られたことを悟り、改心して親鸞聖人の弟子となり、唯円という名をいただきました。(住職談)




立興寺さんを後にして、昼食場所の吉野方面へ。本日は薬膳料理の昼食を頂きました。
どうしても「良薬は口に苦し」の言葉が頭をよぎるので、お味の方はあまり期待できないのでは・・・・・
という不安がありましたが、いい意味で期待を裏切られる事に♫

奈良の吉野には、有名なお寺の金峯山寺があり、昔から山伏たちが山で薬草を使って薬を作ってきました。
また、吉野葛は和菓子や料理に使われる材料で、根っこの部分が薬としても使われていたそうです。吉野の名物「茶粥」には、健康茶や薬膳茶に使われる「大和当帰(やまととうき)」という薬草が入っていて、それを育てている農家も吉野にいらっしゃいます。もともと奈良の吉野には、薬膳料理でお客さんをもてなす文化があったのかもしれませんね。
今回は梅雨真っ只中!前日大雨・当日も雨予報でしたが、奇跡的に傘を使わずに過ごすことが出来ました♫13組の皆さんの日頃の行いの賜物ですね(笑)奈良もオーバーツーリズムで大混雑かと思われましたが、少し観光地から外れるだけで快適に過ごすが出来ました。
事前に心眼寺・松井住職による『歎異抄』のお勉強をさせていただき、それを踏まえて現地に赴き、その土地(寺)の方のお話を聞くのは何にもまさるお勉強になりますね。この度も貴重な時間を皆さんと共有できたことを嬉しく思っております。
さて次はどこへ行きましょう!? (文責 長谷正利)
水平社 日帰り研修
- 2024年06月24日(月)11:56
- コメント: 0
先日、12 組の日帰り研修で奈良県御所市にある「水平社博物館(旧・水平社歴史館)」に行ってまいりました。
御所駅は「JR和歌山線」および「近鉄御所線」の終点に位置しますが、駅からかなり離れているため、今回はマイクロバスで向かいました。
「水平社」とは……
1922 年 3 月 3 日、「人の世に熱あれ、人間に光あれ」をスローガンに、人間の尊厳と平等を大切にするために、全国水平社大会が
京都市岡崎(平安神宮のすぐ横)で開かれました。創立から一昨年で 100 年が経ちました。水平社が発表した宣言は、日本で最初の人権宣言として
今も大切にされています。平和と人権を目指す部落解放運動の始まりは全国水平社にあり、その歴史と精神は多くの先輩たちの努力によって
築かれました。
1986 年、奈良県御所市柏原で地区改良事業が始まり、景色が変わる中で水平社の精神が薄れることが心配されました。この柏原を抜きにして
水平社を語ることはできず、ここでの闘いの歴史を永遠に残したいと考えるのは当然のことです。水平社の創立者たちをはじめ、多くの名もなき
先輩たちが差別に立ち向かって生きてきた事実を掘り起こし、その足跡を保存していくことの重要性を感じ、「水平社歴史館」を建てることに
なりました。
世界人権宣言が国連で採択されてから 50 年が経ち、「人種差別撤廃条約」の批准や「国連人権教育のための 10 年」の決議、日本でも
「人権擁護施策推進法」や「アイヌ新法」が制定されるなど、人権に対する関心が高まっています。この盛り上がりをきっかけに 21 世紀を
人権の時代と位置づけ、先駆的な役割を果たした水平社の世界史的な意義を捉え、水平社発祥の地、御所市柏原を人権のふるさととして
「水平社歴史館」を設立しました。(※水平社博物館 HP より要約)

到着後、ガイドさんの説明を聞きながら館内を巡りました。水平社発足の歴史などがわかりやすく展示されており、また要所要所でガイドさんの
補足説明が入り、水平社博物館が差別撤廃に向けた情報を発信する施設としてどれだけ有用であるかを理解しました。一昨年のリニューアルに伴い、
展示内容は非常にわかりやすく、さらにガイドさんの補足説明も加わり、理解が深まりました。
差別そのものがあった歴史を知らないままでいれば、やがて差別そのものがなくなるのではないかという「寝た子を起こすな論」があります。
しかし、そのような考えでは、最初に聞いた情報が全てとなってしまう恐れが非常に高いため、差別の歴史を「認識」することの重要性を改めて
感じました。
差別・同和問題はその人の取り巻く環境によって全く意見が異なることが予想されます。非常に難しい問題です。私は善悪の分別をつける立場では
ありませんが、それでも今もなお根深く続く差別の歴史を「認識」することは必要だと思います。
そういう意味でも今回の日帰り研修は非常に有意義なものであったと強く感じました。(文責 長谷正利)
「善光寺」研修旅行 三日目
- 2024年06月22日(土)20:05
- コメント: 0
研修旅行最終日。
今朝も早起きして「お数珠頂戴」に善光寺へ♫
この日は地元の路線バスを利用して「オリンピックミュージアム」へ。
今回のメンバーは 1998 年の長野五輪ドストライクの世代。やはり気分が上がりますね♫
入場してすぐにオリンピックのハイライトシーンの上映でおもてなし🎞️
女子モーグルから始まり、スケート、スキージャンプと続きます。

再びバスに乗り、長野駅から帰阪。なかなか内容盛りだくさんの 3 日間でした。
コロナ以降、宿泊を伴った研修旅行が出来ずにいたので、今回は伝研の会メンバーと内容の濃い時間を共有できたように思いました。
やはり現地に足を運んで、その土地の人からのお伝えに耳を傾け、その土地のものを食し、楽しみ、吟味することは何事にも代えがたい貴重な
経験だと感じました。
私事ではありますが、二日目に浄善寺(真宗大谷派)の本堂に通されたとき、何故かホッと安心したことが思い出されます。
3日間に渡りに善光寺(無宗派)のお寺を参拝し、お数珠頂戴・お戒壇めぐりといった参拝形式・修行形式に正直、腑に落ちないところもあったせいかもしれません。「徳」を積む・頂戴する、という行為・考え方にどこかスッキリしないのが原因なのだと思います。
いわゆる「真宗馬鹿」なのかもしれませんね。
しかし、「わかりやすさ」を体現・継続しているのが善光寺なのだということも同時に感じました。善光寺では今も早朝からの参拝者が途絶えません。「観光寺だから」で片付けてしまってはいけないように思います。「お前はわかりやすく仏の教え・先達の教えをお伝えできているのか」と問われているような気がいたしました。(文責 長谷正利)
「善光寺」研修旅行 二日目
- 2024年06月22日(土)19:53
- コメント: 0
研修旅行二日目の朝 5 時過ぎ。
「お数珠頂戴」に参加するため、日の出とともにホテル出発♫
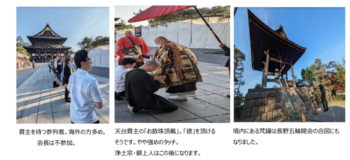

貫主が入堂された後にお朝事が始まります。もちろん 365 日毎日欠かさず勤まります。
外陣・内陣・内々陣と続くのが他の寺院と違ったところ。内陣までは内陣券を購入すると入ることができます。
※堂内写真撮影禁止
御本尊は正面でなく向かって左側にあるのが特徴的。普段は御厨子の中に安置されています。
7 年に一度の秘仏御開帳はよくテレビなどでも取り上げられるのでみなさんもご覧になったことがあるかもしれませんね。
戦国期に御本尊「阿弥陀如来立像」は武田信玄、豊臣秀吉、徳川家康へと渡り、全国へ善光寺信仰を広めるきっかけとなっていきます。
また善光寺には「お数珠頂戴」以外にも「お戒壇巡り」と呼ばれる変わった参拝がございます。
この参拝形式では絶対秘仏の御本尊ですが、実は誰でもご縁を結ぶことができる一種の修行法で、真っ暗な内々陣の地下を歩き、本尊の真下にある「極楽の錠前」に触れることができれば、本尊と結縁し、極楽往生が約束されるというのです。
普通なら一笑に付してしまうのですが、真っ暗闇の中、また決して平坦でもない床の上を歩いて錠前に触れるというのは暗中模索している我々凡夫そのものを体現しているようにも思われました。1400 年以上経っても善光寺が親しまれるのはこういった「わかりやすさ」があるからかもしれませんね。
一度ホテルに戻って、新潟県・妙高市へ移動。
ほとんど長野県との境に位置する「浄善寺」さんへ。
山門を抜けて先ず目に入ってくるのが墓石の数々。後で住職に聞いたのですが、このあたりの墓石は耐雪・耐震・寒冷地仕様で厳重にビス止めされているのだとか。というのも降る雪にはめっぽう強いらしいのですが、溶ける際に日当たりがいい方に墓石がずれていくそうです。
また、この地域では雪を心配して早めに報恩講をお勤めになられるようです。浄善寺さんの報恩講も 9 月に勤まるそうです。
ご住職案内のもと「親鸞聖人・袈裟掛けの松」へ車移動。
親鸞聖人は越後流罪赦免の後に関所があったこの地を通って戸隠や善光寺に向かわれたそうです。その際に松の木に袈裟を掛けて休まれたと伝えられます。現在の「袈裟掛けの松の木」は三代目。初代の松は 1200 年頃なのだそうですが、昭和 13 年になってあまりにも老木、これ以上は倒れて危ないので伐採することに。そして二代目の松を植える際に御門主が来てくださってお手植えされたそうです。
その後は昭和 39 年に道路拡幅工事に伴い再び植え替える事になり今の三代目に至ります。
初代の松伐採の際に、せっかくなのでと、先々代の住職が上越市から彫刻家を呼び寄せて親鸞聖人の坐像を彫ってもらった一つがココに納められています(合計 4 体の内の一つ。2 つは浄善寺に。もう一つは東本願寺に、との文献有り)
その他にも住職には親鸞聖人にまつわる「越後七不思議」のお話もしてくださりました。その一つは「焼き鮒」で、親鸞聖人に供された焼き鮒を池に放したら鮒が生き返った、という言い伝えが残るそうです。(他の 6 つは植物にまつわる不思議)
こういった逸話が残るのは、親鸞聖人が訪ねられた地を、門徒の私達も訪ねることで得るものがあるからだと熱してくださいました。

再び長野県に入り、蓮如上人・ご旧跡「榎御坊」へ。
コチラは住職不在の為、少し立ち寄った程度でしたが、先ず榎がどれなのかわからない(笑)
立派なイチョウはあるのですが。
ありました♫西本願寺の御門主が巡教の際、記念に建てられた灯籠に被っていて見えませんでした(笑)
コチラは親鸞聖人が流罪を許され、関東に行く途中に逗留したとの伝承を残しています。さらに真宗中興の祖・蓮如上人が親鸞聖人のご旧跡を辿ってこの地に来られた際に一本の榎を植えたのが良く繁ったので「榎の御坊」(別名「藤の木のご旧跡」)と呼ばれるようになったそうです。
江戸時代から大正末期まで毎年四月に近隣の信徒が大勢参詣し、門前市を催すほどの宗教上の拠点にまでなっていたそうです。

長野市に戻る道中で小布施に立寄り、昼食と散策♫
小布施といえば、やはり栗♫栗を使ったおこわや和菓子・洋菓子が楽しめます。また、葛飾北斎の作品を展示する「北斎館」があり、美術愛好者には必見の街です。最近では地酒なども人気で食文化も充実した観光地です。
とはいえインバウンド観光客が全く居なかったのが意外でした。
その代わり修学旅行の生徒を街のいたるところで見かけました。
今後の研修旅行はオーバーツーリズムに配慮したコースづくりが必要になるのかもしれませんね。

最後に訪れたのが日本人よりも海外観光客に大人気の「地獄谷野猿公苑」♨
若干疲れの見え始めた伝研の会メンバー。入口の看板を見るなりややげんなりとした様子。
「歩ききった先には素晴らしい光景が待っていますよ」と添乗員にノセられて、往復 3.2 ㌔(登坂あり)のハイキング♫

非常に内容の濃い二日目でしたが、最後のお猿さんたちに癒やされました♫
疲れの出ないことを願って、明日の最終日に備えるとしましょう♫
「善光寺」研修旅行 一日目
- 2024年06月22日(土)15:52
- コメント: 0
先日、伝研の会では長野・善光寺をはじめとした親鸞聖人・蓮如上人のご旧跡巡りに行ってまいりました。
新大阪で集合。名古屋で特急しなのに乗り換え、長野駅についたのは 13 時過ぎ。
「遠くとも 一度は詣れ 善光寺」で有名な極楽往生が叶う寺として 1400 年以上の歴史のあるお寺です。
御本尊は絶対秘仏と言われますが、7年に一度だけ「御開帳」があることでも有名ですね。
そして無宗派のお寺としても非常に有名です。 ※現在は浄土宗の御上人様と天台宗の御貫主様が住職を務めておられます。
まずは親鸞聖人が 100 日間逗留された宿坊「堂照寺」さんへ。
ご案内していただいた鈴木さんのお話によると、親鸞聖人が越後から常陸の国に向かう途中、善光寺に立ち寄られた際、100 日間この堂照坊という宿坊に逗留されたという記録が残っているそうです。
親鸞聖人がこちらに宿泊された理由は 39 軒の宿坊の中でも堂照坊が代々善光寺の御灯明を引き継いできたというのが大きな理由だったと伝えられます。
こういう逸話も残っております。
親鸞聖人が留まられたのは 11 月から 2 月までの約 3 ヶ月間の冬の時期です。堂照坊の源阿房をお供に戸隠山へ行った際、手元にあった熊笹の葉を
使って六字の名号の形を作られたと言われています。これは、松や笹が冬になっても枯れることなく青々としている様子にたとえ、南無阿弥陀仏の
お念仏もどんなに時代が変わろうとも決して枯れることなく続くという意味を込めたものです。
また、堂照坊では、逗留の間に抜け落ちた親鸞聖人の歯が安置されています。

まずは仁王門。両側にはもちろん仁王像。コチラは彫刻家・高村光雲(高村光太郎の父)作のもの。

仲見世通りでは気づくのはいろいろな灯籠が奉納されていて、左右対称ではなくあちこちに立っています。全国からの寄進によるのもがほとんどで、一対になっているものはほとんど無いそうです。
正面に見える「善光寺」の金文字のなかには鳩のシルエットが5つ描かれているのをご存知でしょうか?
「善」の上に2羽、「光」の上に2羽、最後は「寺」の点に一羽。
最初はいがみ合っていた鳩も次第に仲睦まじく向かい合い、最後は左(西)を向いて飛び立っていった、とされ、これは西方極楽浄土を意味するとされているそうです。